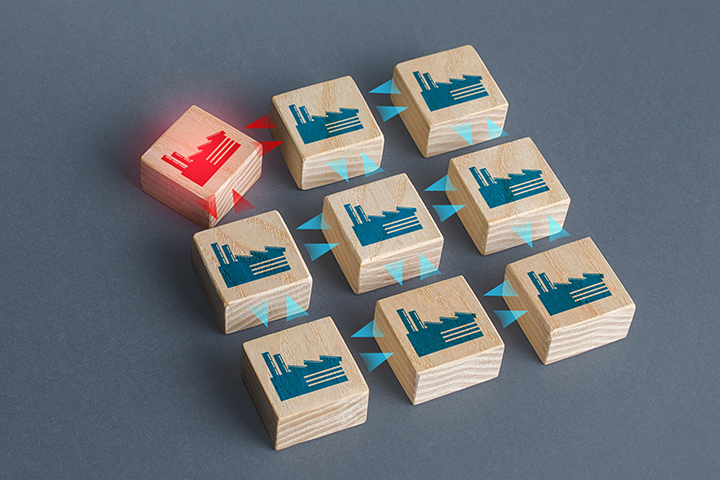本当に役立つITコンセプトの作り方
成功するシステム導入プロジェクトへの道標
- お役立ち情報
2025年07月22日
ITシステムの構築にかかわらず、あらゆるプロジェクトの成否は、施策や導入する技術の良し悪しよりも、そもそもどのような効果を狙うのかというプロジェクト自体のコンセプトに大きく依存します。良いコンセプトとは「何かをより良くしたい」というプロジェクトチームの思いを具現化したものです。そして、コンセプトは、チーム全体の共通理解を形成し、チームが原点とする行動指針として、あるべきITシステムを実現するための道標となります。企業を取り巻く状況が激しく変化する中では、当初の計画に固執するのではなく、軌道修正を自ら判断できる柔軟な対応が求められます。そうした中でコンセプトは道標として重要な役割を果たします。
目次
なぜITシステムの構築プロジェクトでコンセプトが必要なのか?
ITシステムの構築プロジェクトにおいて、その成否の鍵を握るのはコンセプトの有無にあると言っても過言ではないでしょう。そもそもなぜコンセプトが必要なのでしょうか。私たちは幼少期から計画の大切さを教えられ、社会に出てからもPDCAのサイクルを重視してきました。しかしその弊害として、状況が変わっても計画を遵守することに縛られがちです。もちろん計画がなければ、プロジェクトは成り立ちません。ひたすら行動あるのみといった、実行一辺倒のアプローチではチームは迷走してしまいます。
重要なのは、このどちらかに偏るのではなく、時と場合に応じた柔軟な軌道修正です。状況変化に応じて絶え間ない軌道修正を自らの判断で行っていくことが必要で、コンセプトはまさにその道標となります。
コンセプトは理想の世界に向かっていくプロジェクトチームやリーダーの思いが具現化したものともいえます。すなわちITシステムの構築プロジェクトにおけるコンセプトは、その後に続くプロジェクトの価値を明確にし、新しいアイデアを生み出すとともに、賛同を得て協力者や活動資金などのリソースを確保し、プロジェクトに推進力を与えるといった多くの効果をもたらします。
重要なのは少数精鋭チームでコンセプトを作り切る覚悟
どうすれば良いコンセプトを打ち出すことができるでしょうか。まず強く訴えておきたいのは、少数の仲間でコンセプトを作り切る覚悟を持つことです。
コンセプトは前述の効果でも示したとおり、多くの人を巻き込み、賛同を得るものである必要があります。こうしたことから「組織全員の思いの共通部分を取り入れよう」「できるだけ民主的に議論を進めよう」と、多くの人が考えるのではないでしょうか。
しかし、そこに大きな落とし穴があります。全員の思いの共通部分といえば聞こえは良いのですが、裏を返せば誰にとっても「自分の思いに近いけれど、完全に自分の思いと同じではない」という広く浅いコンセプトとなってしまい、結果として当たり障りのないものになりがちです。
これに対して、ごく一部の精鋭メンバーでコンセプト作りを進めるケースはどうでしょうか。こちらは少数であるがゆえに、偏り尖ったものになるのは想像に難くありません。それを関係者間でぶつけ合いながら、最終的には民主的な形で合意を取る方法がよいでしょう。
あえて偏り尖ったコンセプトを他人と共有することが、活発な議論を呼び起こすきっかけとなることもよくあります。そうやって揉まれながら昇華させていったコンセプトが、プロジェクトにおいて力強い推進力を生み出すことになります。

メンバー選定には特別なルールはありません。例えば、全社的に利用するITインフラやアプリケーションに関するコンセプトを作るのであれば、情報システム部門の人材だけでなく、営業部門や経理部門などのエンドユーザーもメンバーに加えることがよくあります。一方、特定領域の課題解決を目指したコンセプトを作るのであれば、その影響を直接受ける当事者のみでメンバーを構成しても構いません。
コンセプト作りの議論は「鉄は熱いうちに打て」という格言にもあるとおり、2日間くらいの短期集中で行うことをお勧めします。ワークショップや合宿を開催するのもよいでしょう。
3つのステップで作成するITコンセプト
コンセプトは「課題から気づきの抽出」「解決ストーリーの検討」「コンセプトの言語化」という3つのステップで作成していきます。

最初の「課題から気づきの抽出」段階では、メンバーの日頃の葛藤を基に、理想を探ることから始めます。付箋1枚に課題を1つずつ書き出し、説明し合います。正しいかどうかを気にせずに、チームに議論を投げかける気持ちで挙げていくのが重要です。
次にそれらを本質が近いグループでまとめ、ラベルを付けます。表面的な類似性や先入観でグループ化するのではなく、課題の背景にあるものを捉えることがポイントです。グループ分けやラベル付けに正解はありませんが、アイデアを聞いた際にメンバーの半数が「どういう意味?」と疑問を感じるくらいが、新しい視点としてちょうどよいでしょう。
課題から解決までのストーリーを描く
課題のグループ分けとラベル付けが終わったら、ステップ2に移ります。実はステップの中で最も難しいのが、この「解決ストーリーの検討」です。自分たちが出した課題やこうなりたいというビジョンが、組織全体にどのように波及していき解決に向かうのか。その流れを検討し、一筆書きが通るラベルをなぞりながら、課題から解決へ至る大きな川の流れをイメージして、1本の道筋を描きます。

課題から解決までを1本のストーリーにまとめることにより、一貫性を持った文脈として、全員で共有することが可能となります。1本のストーリーができたら、課題から解決に至るルートをどのように実現するか、HOW(手段)を検討し、ルートに追加して完成させます。
コンセプトを簡潔な言葉で伝える
ストーリーを誰もが覚えやすい簡潔な言葉にするのが、最後の「コンセプトの言語化」ステップです。
このステップで重要なポイントの1つ目は、人によって解釈が分かれる言葉を使わないことです。よく陥りやすいのが「○○DX」や「○○テック」「○○2.0」など、流行り言葉を安易に使ってしまうことです。こうした言葉を使えば、現在のトレンドを踏まえているイメージをなんとなく醸し出せるでしょう。しかし、その受け止め方は相手の担当業務や役職、あるいは課題に対する理解度やITのスキルレベルによっても大きく異なってきます。結果的にコンセプトの背景にある意図が正確に伝わらず、言葉だけが独り歩きして認識に大きなズレを抱えたまま、プロジェクトが進む恐れがあります。
2つ目のポイントは覚えやすいように1文で簡潔な表現にすることです。できれば20文字程度に収めるくらいの割り切りが必要です。

プロジェクト成功へコンセプトが果たす役割
以上のステップを経てポイントを押さえたコンセプトを打ち出すことで、その後のITシステムの構築プロジェクトをスムーズに進めていくことができます。要件定義から設計・構築フェーズ、運用・保守フェーズへと至るプロジェクトの節目で、仮に主たるプレイヤーが代わったとしても問題はありません。コンセプトさえしっかり共有できていれば、目的がぶれることはないからです。
さらにコンセプトが大きな効果を発揮するのが、導入したITシステムの定着化や利用拡大の局面です。企業が抱えるさまざまな課題に対して、ITシステムの導入により解決が可能な部分は、実のところ全体の2~3割にすぎません。単にITシステムを導入するだけで即座に課題が解決し、会社が劇的に改善されるという夢物語はありません。
残りの7~8割に及ぶ課題を解決するためには、ITシステムに関連付けられた業務プロセスの再設計や、ITシステムを効果的に活用する人材の育成、マインドセットの変更が不可欠です。最終的には、誰がどのように行動すべきか、あるいは何を目指すのかという人の問題に帰結することになります。こうした人を巻き込み、動かしていく上で、コンセプトが重要な役割を果たします。
一方で、コンセプト作りを社内だけで進めることは難しい場合もあります。社内の視点だけでは目の前の現状や常識に無意識に縛られたり、部門ごとの立場や利害が異なることにより遠慮や妥協が生まれたりすることで「本当に追求すべきコンセプト」よりも「全員が納得できる無難なもの」になりがちです。また全体から俯瞰して課題を捉え切れず、限られた視野の中だけでコンセプトを作ってしまうリスクもあります。
そのような場合は、第三者を入れる方法も検討しましょう。社外のプロフェッショナルが入ることで議論の質が高まり、意見が対立しても中立的な進行役がいることで建設的な議論を続けやすくなります。このようにコンセプトを適切に策定する手段として、社外のITコンサルタントを活用するのも一考でしょう。
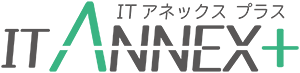
関連情報
関連商品・サービス
関連ソリューション
関連事例
関連コラム
お問い合わせ
お客さまの立場で考えた、
最適なソリューションをご提供いたします。
お気軽にお問い合わせください。